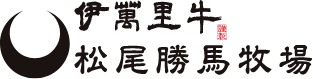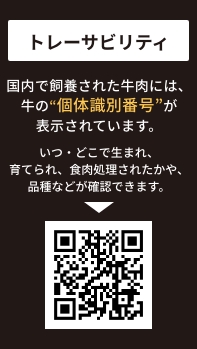スタッフブログ
2025年9月20日
日本のホルモン食文化の歴史
日本のホルモン食文化の歴史
今では焼肉やもつ鍋の定番として親しまれているホルモン。
しかし、かつては「捨てる部位」とされてきた歴史があります。
この記事では、日本におけるホルモン食文化の歩みをたどりながら、伊萬里牛ホルモンがどのように受け継がれ、発展してきたのかをご紹介します。
戦前・戦後とホルモン文化のはじまり ⏳
ホルモン料理の歴史は、戦前から戦後にかけて庶民の間で広まりました。
当時、内臓肉は「放るもん(捨てるもの)」とされ、ほとんど食用にはされていませんでした。
しかし、食糧難の時代に「もったいない」と工夫して調理されるようになり、徐々に食文化として定着していきます。
もつ料理の広がり 🍲
関西や九州を中心に、内臓を使った「もつ焼き」や「もつ鍋」が庶民の味として広がりました。
特に博多では、戦後に屋台から始まったもつ鍋文化が人気を博し、寒い季節に体を温める定番料理となりました。
焼肉ブームとホルモン人気の定着 🔥
1960年代以降、焼肉文化が日本全国に広がると、ホルモンも「安くて美味しい部位」として人気が定着しました。
「ホルモン焼き」や「シロ」「ミノ」などの部位が日常的に食べられるようになり、内臓肉が特別なものではなく、一般的な食材として認識されるようになったのです。
現代のホルモン文化と伊萬里牛 ✨
現代では、ホルモンはただの庶民料理ではなくグルメ食材として注目されています。
特に伊萬里牛のホルモンは、と畜場から直接受け取り、自社で洗浄・カット・急速冷凍までを一貫して行うため、鮮度抜群・臭みが少なく・プリプリ食感を誇ります。
「放るもん」だったはずの部位が、今では贅沢な一品として食卓を彩る存在となっています。
まとめ ✅
日本のホルモン食文化は、戦後の食糧難をきっかけに「捨てる部位」から「美味しい料理」へと進化してきました。
焼肉やもつ鍋として定番化した今も、地域ごとに独自の食べ方や楽しみ方があります。
特に伊萬里牛ホルモンは、その歴史を受け継ぎながら新鮮で高品質な味わいを届ける特別な存在です。
ぜひご家庭で、歴史とともに進化したホルモンの美味しさを味わってみてください。